IT業界ではおなじみの「二次請け」「三次請け」という言葉。
下請けのシステムエンジニアには、苦労話が絶えません。
元システムエンジニアの僕自身も、下請けの中小企業に勤めていました。
「残業、休日出勤は当たり前」
「ストレスとの戦い」
「やりがいを感じない」
そんな悩みを抱えた結果、30代を過ぎてもシステムエンジニアを続ける自分の姿が想像できず退職しました。
そこで今回は「下請けのシステムエンジニアはきつい」をテーマに、30歳で抜け出した理由を紹介します。
この記事でわかること
- 下請けのシステムエンジニアを抜け出した理由
- フリーランスを選んだ理由
- 退職の負担を減らすためのポイント
下請けのシステムエンジニアを抜け出した理由

下請けの中小企業でシステムエンジニアとして9年間働きました。
しかし、以下の理由で限界を感じて抜け出しました。
- 人手不足に陥りやすい
- スキルに見合った業務ができない
- 精神論で解決しようとしがち
- 納期に悩まされる
- やりがいを感じられない
前職を辞めたときの年齢は30歳。
20代に精神をすり減らし、気力を失いました。30代にさしかかり、体力の限界を感じるように。
数年先の将来を考えたとき、今のストレスが続くのかと思うとゾッとしました。
人手不足に陥りやすい
下請けの中小企業は、人手不足に陥りやすい傾向にあります。以下は、そのおもな要因です。
- 社内のリソースが不足している(社員がすぐやめる)
- 社員のスキルが不足している(負荷が偏りがち)
- 無理な案件を受注している(見積があまい)
下請けの中小企業は、基本的に30〜50名程度の社員数です。また、社員の入れ替わりも激しいです。
「人数が少ない=少数精鋭」と前向きな表現では誤魔化せません。
特定の社員にスキルが偏ってしまうことも多々あります。
業務を負荷分散できないことは、プロジェクトの進捗を遅れさせるボトルネックとなりかねません。
スキルに見合った業務ができない
下請けのシステムエンジニアは、基本的にスキル以上の業務を求められます。
おもな要因は「案件ありき」の業務体制です。
- まずは案件を受注する
- 手すきのメンバーを当てはめる
- 案件に必要な知識を習得しながら業務(同時進行)
中小企業が限られた人員で利益を生み出すためには、案件を選ぶ余裕なんてありません。
さらには、案件を受注するたびに新たな知識やスキルが必要となることも。
しかし、下請けの中小企業は、案件にベストマッチな社員を都合よくアサインできません。
プロジェクトメンバーのアサインは、ハッキリ言って「消去法」です。
精神論で解決しようとしがち
下請けのシステムエンジニアは、しんどい状況を精神論で解決しようとします。
なぜなら、ほかに解決する術がないからです。
僕が務めていた会社も壁一面に「モチベーションアップ株式会社」のポスターを貼っていました。
ポスターに記載された内容は、たしかに正論です。
間違っているとは思いません。
しかし、問題の解決につながったことはありません。
モチベーションには、問題から気持ちをそらす効果しかありませんでした。
「しんどい経験があったから」は、人が成長する理由にはなりません。
成長するための手段に「しんどい思いをする」が通用するわけがない。
納期に悩まされる
下請けのシステムエンジニアは、納期に悩まされます。僕自身がエンジニアを辞めた一番の理由です。
- タイトなスケジュール
- 想定どおりに進捗しない
- 急な仕様変更を依頼される
基本的にスケジュールのバッファ(余力)を持つことはありません。
遅れる前提ではスケジューリングさせてもらえない。
とはいえ、ほとんどのプロジェクトは想定外のトラブルに陥ります。
一部の機能が実装できなかったり、
メンバーの進捗が遅れたり(スキル不足、体調不良)、
急な仕様変更を依頼されたり…
立場の弱い下請け企業は、簡単に納期を変更できません。
納期に間に合わせるためには、残業や休日出勤での対応を余儀なくされます。
やりがいを感じられない
下請けのシステムエンジニアは、やりがいを見失うこともあります。
本来であれば、システム開発はシステムを使用するユーザーのために行うべきです。
しかし、いつしか元請け企業(取引先)のために開発していることに気がつきます。
僕自身も過去に忘れられない出来事がありました。
元請け企業が用意したツールを苦労して徹夜でシステムに実装した。
しかし、エンドユーザーから「ツールが使いづらい」と不評だった。
後日、機能強化の案件で「あのツール全部消して」と要望を受ける結果に。
あのときの苦労は何だったんだ…
どれだけ良いシステムを開発しても、頑張りを評価してくれるのは取引先(元請け企業)です。
苦労して開発したシステムをエンドユーザーから「いらない」と評価されたとき、下請け企業にやりがいを感じられなくなりました。
フリーランスを選んだ3つの理由
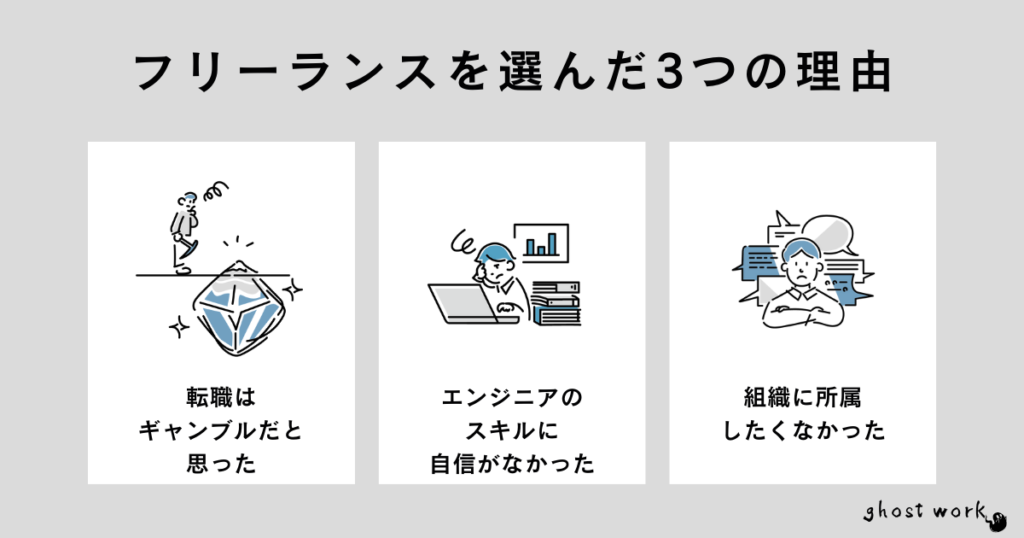
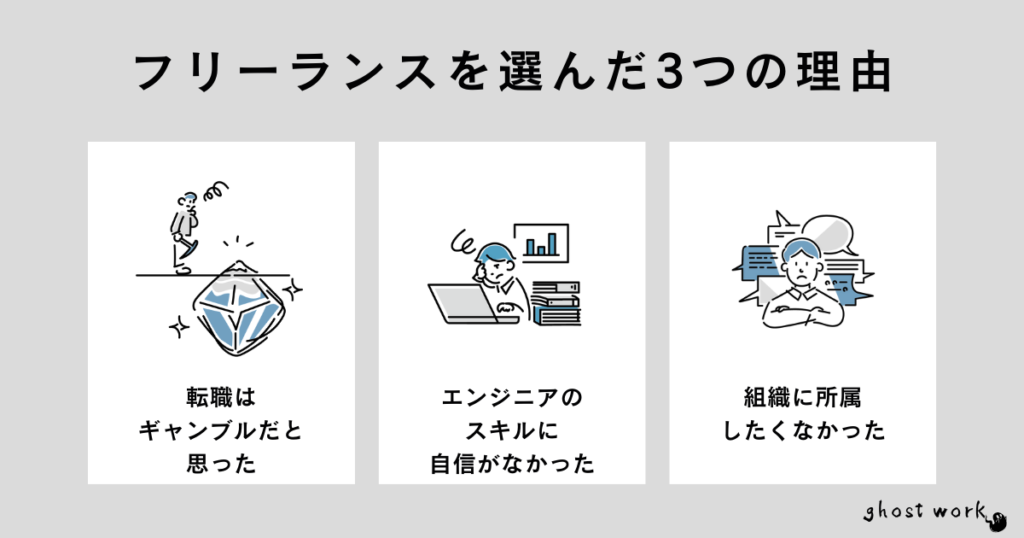
下請けのシステムエンジニアを辞めた後は、フリーランスの道を選びました。
もちろん、ほかの企業へ転職する選択肢もありました。
しかし「転職」に対して、ネガティブなイメージをぬぐい切れませんでした。
転職はギャンブルだと思った
システム開発会社への転職には「状況が悪化したらどうしよう」といった不安が残ります。
とくに「職場環境」や「人間関係」は、自分でコントロールできるものではありません。
そもそも退職した会社も、最初は期待をもって入社したはずです。
正直、転職先が「今より良いかどうか」は、入社してみないと判断できないのではないでしょうか。
フタを開けてみないと分からないのであれば、ほとんどギャンブルするのと同じだよね。
エンジニアのスキルに自信がなかった
元請けのシステム開発会社は、基本的には大手企業です。
転職を目指す場合は、即戦力レベルの技術力が求められます。
しかし、自分には、アピールできるほどの技術力がありませんでした。
社内での評価が他社では通用しない(伝わらない)ことを痛感しました。
業務を必死に頑張れば、社内では評価してもらえます。
しかし、会社の外に出れば、その評価は何の役にも立ちません。
もちろん、現状のスキルで転職できるシステム会社もあります。しかし、ほとんどが下請け企業でした。
組織に所属したくなかった
すごく個人的なことですが、組織に所属することにストレス(煩わしさ)を感じるようになりました。
- 報連相の伝言ゲームに疲れた
- 上司や部下に気をつかうのが疲れた
- ルールに従うことに疲れた
フリーランスでも、チームで動くことはあります。
しかし、企業にいるよりは、自由な選択肢で行動できていると実感しています。
もちろん選択した行動に対する責任感もあります。
自分で選んだ選択肢だからこそ、正面から喜びや反省に向き合えます。
組織に所属しているときより、他人への不満を感じる頻度が減りました。
退職後の負担を減らす3つのポイント
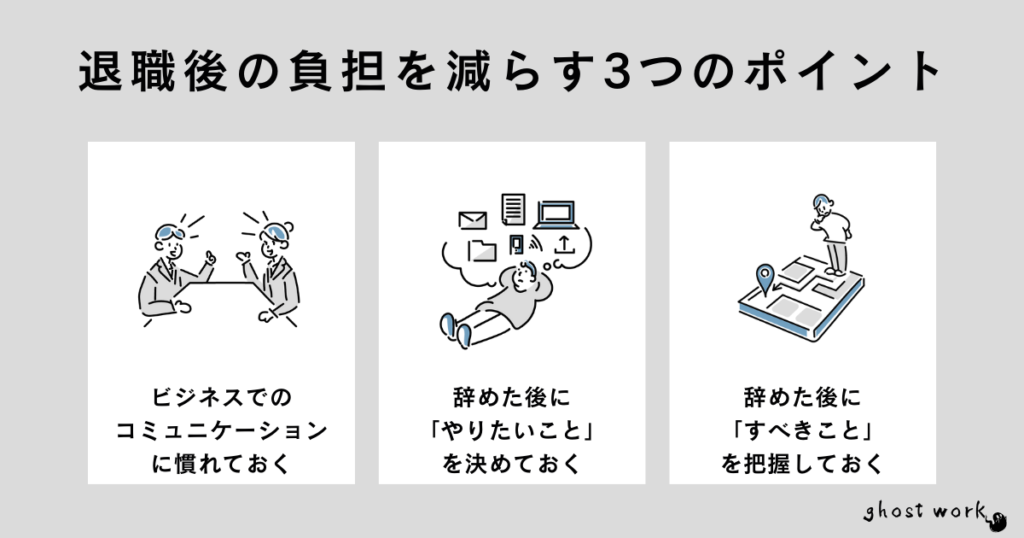
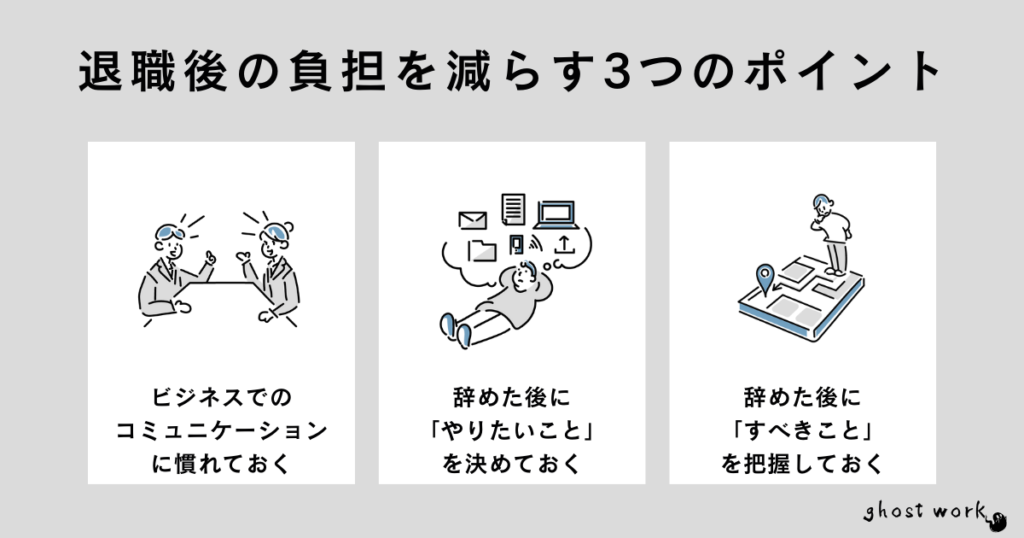
退職後の負担を減らすためにも、
個人的に「やっておいて良かった」「やっておけば良かった」と感じた3つのポイント
を紹介します。
- ビジネスでのコミュニケーションに慣れておく
- 辞めた後にやりたいことを決めておく
- 辞めた後にすべきことを把握しておく
ここで紹介する内容には「スキルアップやリーダー経験」のような理想論はありません。
退職までにやっておきたいことは山ほどあります。もちろん必要なスキルは習得すべきですが、忙しい業務と並行してできることには限界があるはずです。
僕自身は転職活動をせず、勢いで退職しました。辞めてからでも十分に間に合いますし、重要な選択ほど焦って判断すべきではありません。
ビジネスでのコミュニケーションに慣れておく
今後の選択肢にかかわらず、社会人としてビジネスのコミュニケーションに慣れておくことは重要です。
- メールのやり取り
- 対面での言葉づかい
- アポの取り方・タイミング
退職後は、社会人としてかかわるすべての人が初対面です。
つまり、一発目のコミュニケーションが第一印象を大きく左右します。
とくにフリーランスは、コミュニケーションから「社会人経験がなさそう」を感じる人もいます。
相手の立場や状況を配慮してコミュニケーションできれば、少なくとも悪い印象は与えません。
辞めた後にやりたいことを決めておく(候補でOK)
退職後の方向性を定めるためにも、やりたいことの候補を決めておきましょう。
大まかな目標を決めるようなイメージで問題ありません。
- フリーランスに挑戦したい
- 失業保険は貰っておきたい
- 半年間は趣味の時間に使いたい
退職後の数ヶ月間は自由な時間が増えます。そのせいか、時間の経過する感覚があっという間です。
なにもしないまま数日が経過すると、意外に焦りが出てきます。
事前にやりたいこと(ゴール)を決めておけば「これからどうしよう?」と迷う時間を減らせます。
辞めた後にすべきことを把握しておく(手続き・準備など)
退職後は会社の手続きや市役所での申請など、やるべきことがたくさんあります。
- 必要書類の受け取り
- 備品の返却
- 国民健康保険への切り替え
- 国民年金への切り替え
- 確定申告の手続き
- 失業保険の手続き
- マイナンバーカードの発行
- 開業届・青色申告承認申請書の提出(フリーランスの場合)
市役所や税務署で行う手続きには、必要書類や対応期限があります。
必要書類の準備に手間がかかることもあるため、やるべきことは事前に把握しておくと安心です。
後悔したこと|もっと早く辞めれば良かった


下請けのシステムエンジニアだった頃は、毎日「辞めたい」と思いながら働いていました。
とはいえ、そんな自分にとっても、退職することは大きな決断でした。
いざ退職して、一つだけ後悔したことがあるとすれば、
もっと早く辞めれば良かった。
と感じたことです。
退職してフリーランスとなり、新たなジャンルで仕事を始めました。
フリーランスとして達成したい「5年後の目標」を考えていたとき、ふと思いました。
もし、5年早く退職していたら、すでに目標を達成していたかもしれない。
新しいことへの挑戦は、想定どおりに進まないことも多く、成果が出るまで時間がかかります。
一般的には「退職=逃げること」のような、ネガティブなイメージがあるかもしれません。
しかし、あくまでも「一つの行動」と捉えれば、早めに決断しておくべきだったと後悔しました。
【疑問】下請けのシステムエンジニアは辞めるべきなのか
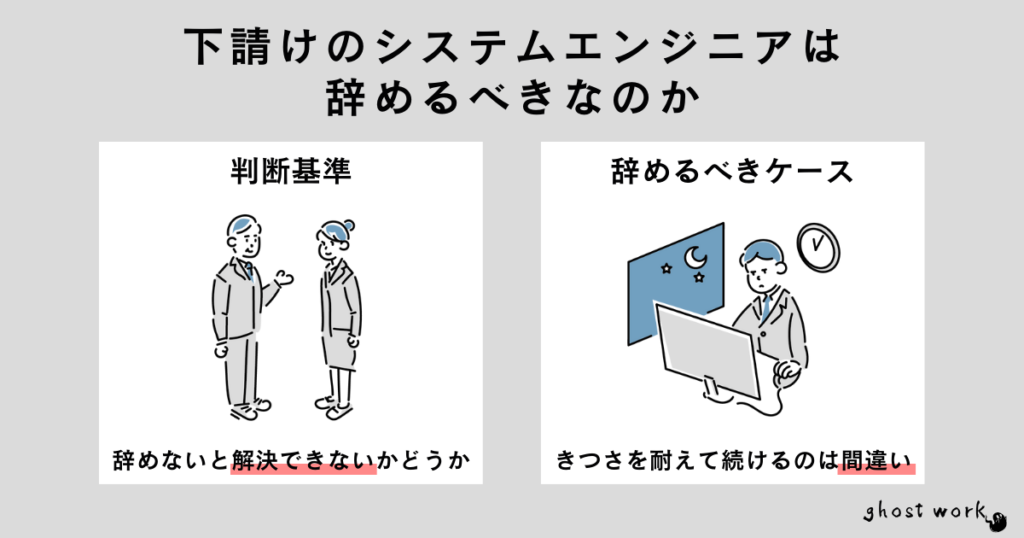
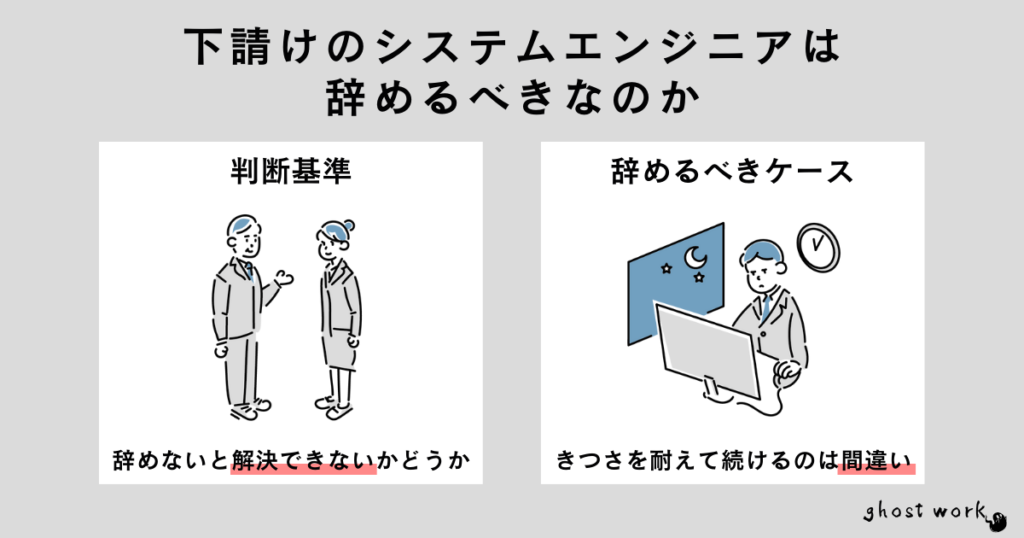
ここまで、下請けのシステムエンジニアの悪いところを「これでもか!」と紹介しました。
今現在、下請け企業で働いている人は「じゃあ辞めたほうがいいの?」と感じるかと思います。
ですが、最後に一呼吸おいて「本当に辞めるべきかどうか」を考えてみてほしいです。
結論|本当は辞めずに済むのが理想
システムエンジニアにかかわらず、せっかく入社した会社は辞めずに済むのが理想的です。
今の仕事を続けていれば、毎月一定額の収入を得られます。
安定した収入を得られることって「当たり前」ではありません。
退職したい理由が「辞めないと解決できないことかどうか」を考えることも大切です。
しんどいときはネガティブな発想ばかり浮かんでしまいがちですが、退職ほどリスクの大きな選択肢はありません。
あくまでも「解決策を失ったときの最終手段」として、退職するかどうかを判断しましょう。
僕自身も上司との人間関係に悩んだときは、部署を異動させてもらいました。
きつさを耐えて続けるのは間違い
ストレスにより心身の健康を保てない場合は、ガマンせずに退職を検討すべきです。
- 職場の人間関係
- 労働時間の長さ
- 業務や社風が合わない
どんな仕事でもつらい時期はあります。しかし、心身に不調が現れる状況は「異常」と判断すべきです。
とくに「人間関係」や「職場環境」の悩みは、一人で頑張っても解決できません。
悩みや不調を抱えた状態では、仕事を続けたところで集中力を欠いてしまいます。
退職は「逃げ」ではありません。仕事を真剣に続けるためにも、新しい環境での再スタートを検討してみましょう。
下請けのシステムエンジニアはきつい|新しい環境を探してみよう
今回のまとめ
- 人手不足に陥りやすい
- スキルに見合った業務ができない
- 精神論で解決しようとしがち
- 納期に悩まされる
- やりがいを感じられない
- 転職はギャンブルだと思った
- エンジニアのスキルに自信がなかった
- 組織に所属したくなかった
- ビジネスでのコミュニケーションに慣れておく
- 辞めた後にやりたいことを決めておく
- 辞めた後にすべきことを把握しておく
きつさを耐えて続けるくらいなら、新しい環境で再スタートしよう!
下請けのシステムエンジニアは、きついと感じることが多々あります。
僕自身も取引先の無茶ぶりに「自分ではどうしようもない」と感じ、退職を決心しました。
小さなストレスのきっかけが、人間関係や心身の健康に波及することもあります。
きつさから逃れることに遠慮せず、自分が「前向きに頑張れる場所」を探してみましょう!
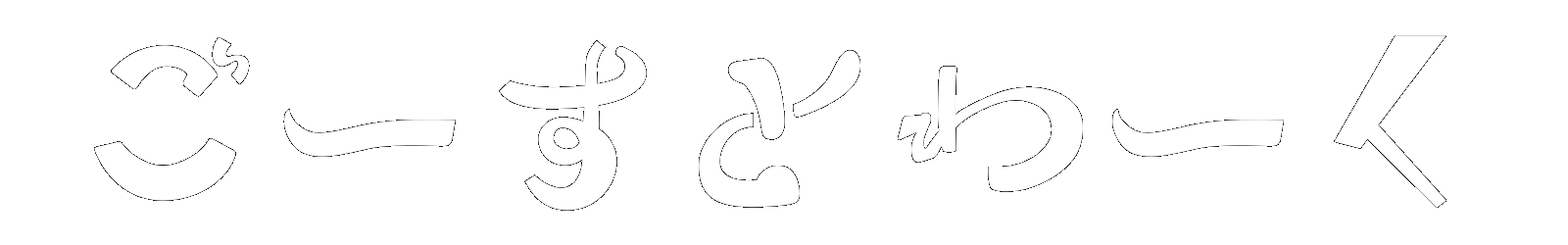
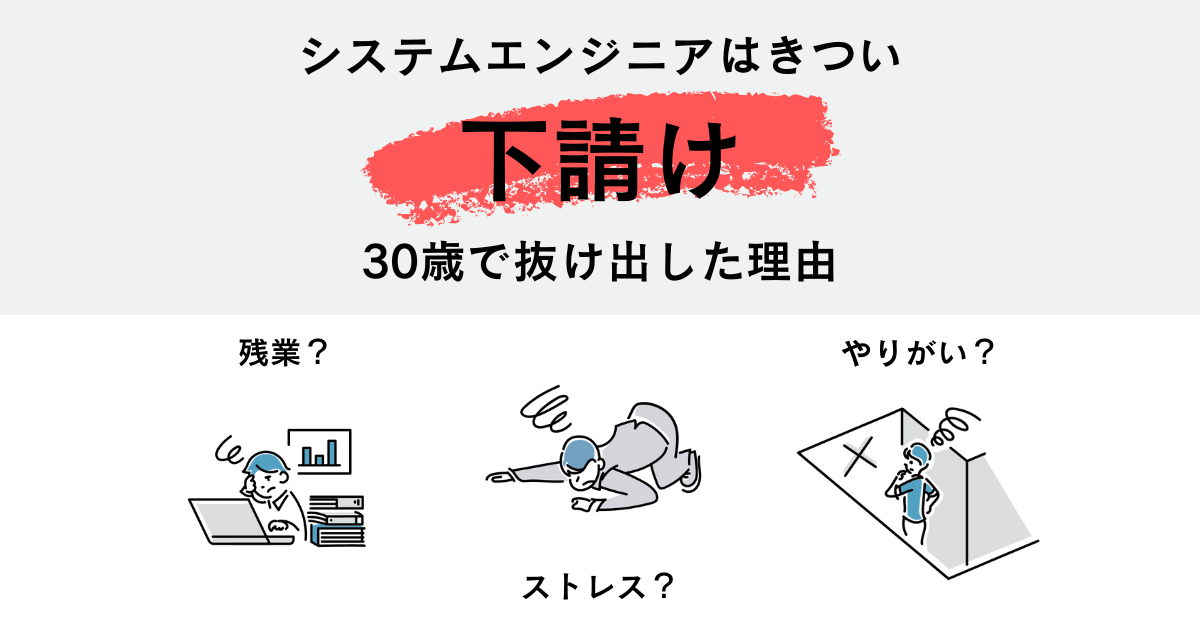
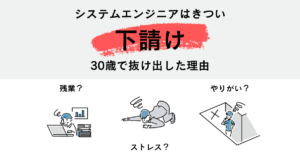
コメント