システムエンジニアの頃は、きついプロジェクトを任されることが日常茶飯事でした。
しかし、とあるプロジェクトで「さすがにギブアップしようかな」と考えたことがあります。
めちゃくちゃ短納期の依頼。しかも、ズラせない。
開発担当の人手が足りない。募集する時間もない。
そんな窮地を救ってくれたのが、オフショア開発を依頼したベトナムのエンジニアでした。
今回は、そんなベトナムのエンジニアが「感心するほど超優秀だった」って話です。
この記事でわかること
- ベトナムのエンジニアが優秀だと感じた理由
- ベトナムへのオフショア開発で気になったこと
(メリット・デメリット)
高負荷・短納期の案件に頭を抱えていた

2018年9月のこと。
軽減税率対応(2019年10月)に向けて、システム改修の依頼を受けました。
2019年4月のこと。
クライアントがシステム改修の要件定義を進めているはずだが、一向にまとまる気配が見えない。
状況を確認すると、どうやらクライアントとエンドユーザーと揉めている様子。
- 「言った、言わない」の水掛け論
- 担当者同士が知り合いで犬猿の仲
- お互いに不親切で話がまとまらない
気がつけば2019年6月に差し掛かり、ようやくクライアントから「開発をお願いします」の声が。
与えられた開発期間は約4ヶ月。
クライアントが上流工程(要件定義~概要設計)で約1年間ケンカした結果、高負荷・短納期のモンスター案件が生まれました。
結局いつも下請けに負担がかかるんだよな…
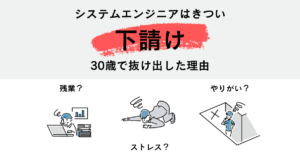
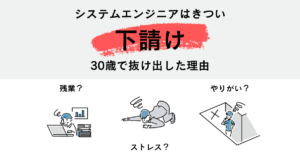
高負荷|社内のリソースでは人手が足りない
システム改修にかかわる機能は「約100画面」。
しかも、当初は想定していなかった改修まで追加されているオマケつき。
ざっと見積もっても「30人月」は必要でした。
うちの会社、在籍人数35名なんです。
総動員で対応しろと?
短納期|緊急すぎて外部委託できる取引先がない
不足するリソースを確保するため、外部委託できる得意先を探すことに。
しかし、急な依頼となってしまったため、求める人材を確保できない。
複数の得意先に数名ずつの外注を依頼するにも、さすがに効率が悪い。
やる気が出ない。
ギブアップしてもいいかな?
【結果】ベトナムにオフショア開発を依頼した
システム開発を海外企業のエンジニアに委託する開発手法。
人件費の安いアジアを中心に活用する企業が増加している。
あまりにも悪化する状況に落ち込んでいたところ、
別案件を担当していた同僚から「ベトナムに相談してみようか?」と提案を受けた。
じつは同僚も似たようなモンスター案件を対応しており、ベトナムへのオフショア開発を依頼していた。
タイミングよく案件が終了したので、ベトナムのエンジニアに継続対応を依頼してくれることに。
開発担当者は約20名。単価は日本の半分程度。
「本当に大丈夫かな?」と少し疑心暗鬼になりながらも、ほかの選択肢がなかったのでオフショア開発を決断。
結果的にベトナムの超優秀なエンジニアに救われました。
ベトナムのエンジニアが「超優秀」だった
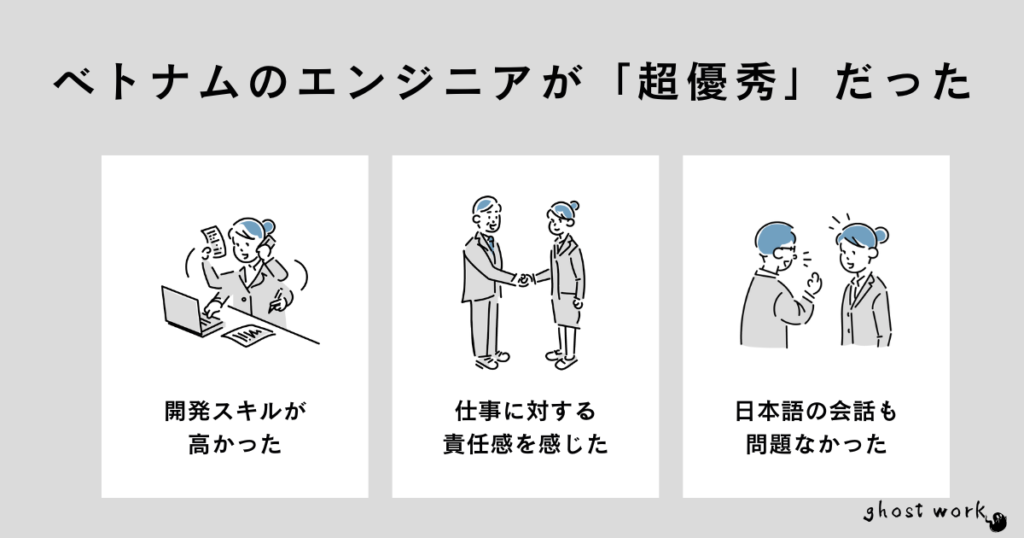
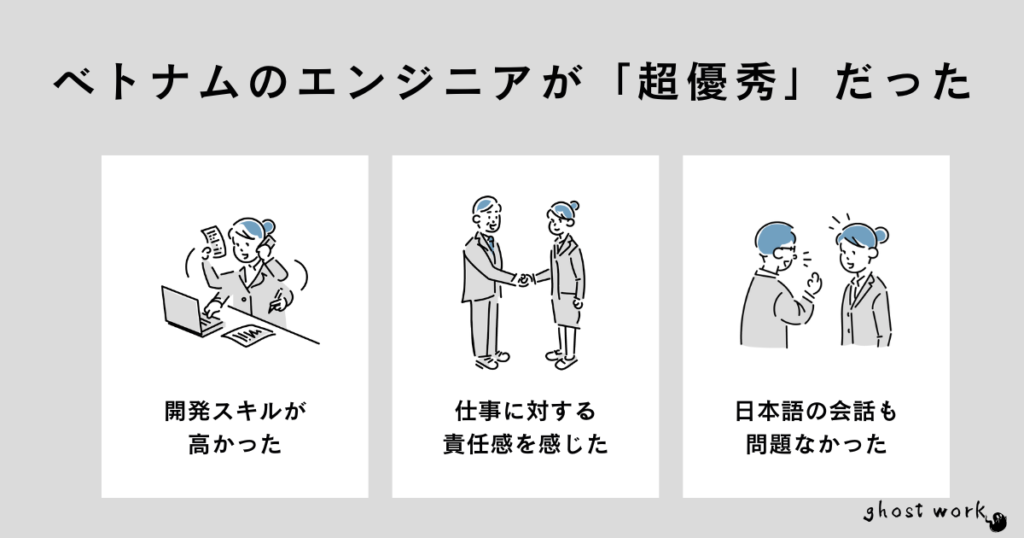
ベトナムのエンジニアは、開発スキルも取り組む姿勢も「超優秀」でした。
もしかすると、自分がかかわる日本のエンジニアが「低レベル」だったのかもしれません。
少し強めの言葉を選びましたが、それくらいオフショア開発したことで助けられました。
開発スキルが高かった
ベトナムのエンジニアには、開発スキルの高さを感じました。
開発スキルに長けているのはもちろんですが、どのような開発言語にも対応できる人員が揃っていました。
しかも、開発環境まで自前で用意してくれる心強さ。
「メンバーも環境も要望に応じて準備するから何でも依頼して。」ってスタンスでした。
国内で開発案件を依頼すると、スキルがマッチしない場合に断られることがほとんどです。
もちろん自分が勤めていた会社も例外ではなかったので、ベトナムの柔軟な対応力には感心しました。
仕事に対する責任感を感じた
ベトナムのエンジニアには、仕事に対する責任感を感じました。
これは海外から出稼ぎに来ている外国人に対しても、たびたび感じることです。
- 責任をもってできる範囲をしっかりと線引きする
(やることはきっちりやる・できないことはキッパリと断る) - 必要なことは積極的に問い合わせしてくれる
- 改善案を積極的に提案してくれる
まじめに働くことは、当たり前のことだと思います。
しかし、当時の自分は、誠実さに欠ける社員の扱いに悩んでいました。
- やりたいことは積極的にやる
- やりたくないことは平気で断る(もしくは嫌がる)
「社畜のように従え」と言うつもりはありません。
ただ、立場をわきまえずにわがままを言う社員に心底疲れていたので、誠実な対応がうれしく感じました。
日本語のコミュニケーションも問題なかった(ブリッジSEがいた)
ベトナムの開発部隊には「ブリッジSE」と呼ばれる担当者がいました。
海外企業へのオフショア開発において、日本企業との橋渡し役となるシステムエンジニア。
外国人担当者との意思疎通をサポートしてくれる。
日本語対応できるブリッジSEが窓口担当となってくれたので、円滑なコミュニケーションでやり取りできました。
週1回のWeb会議でコミュニケーションをとっていました。
製造(コーディング)担当のエンジニアには、日本語がわからない人、少しだけならわかる人もいるとのこと。
そのため、ブリッジSEの存在は、円滑なコミュニケーションには必要不可欠でした。
ベトナムへのオフショア開発で気になった5つのこと
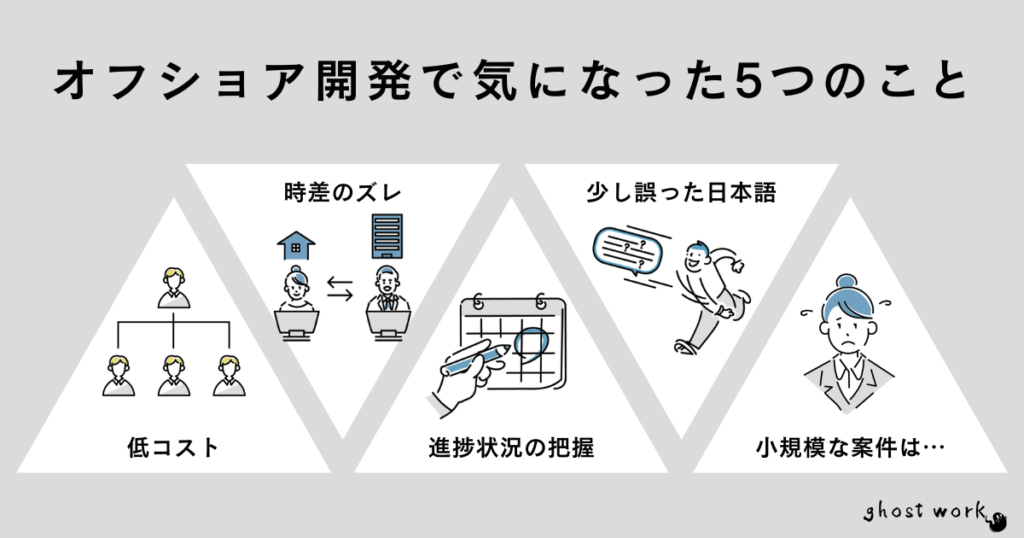
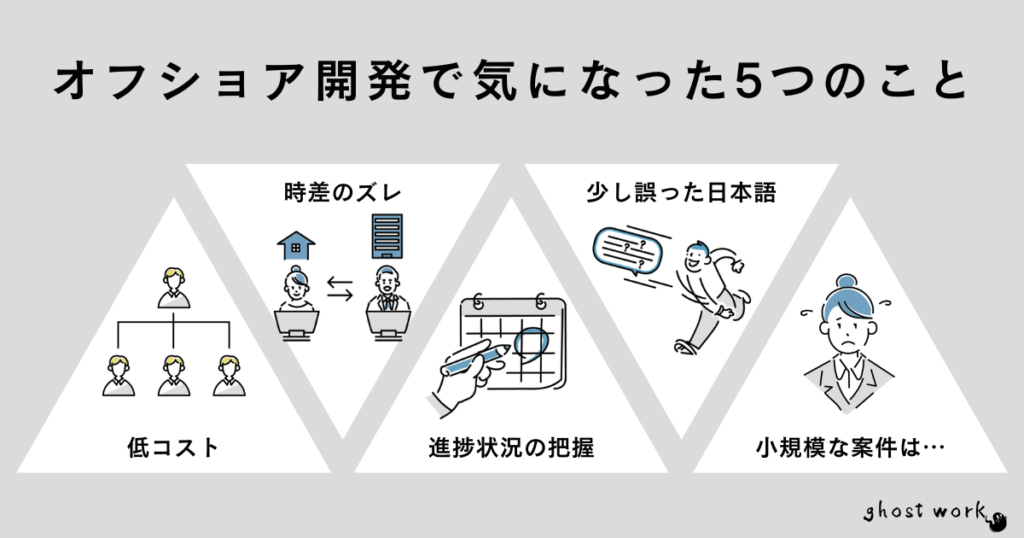
頭を抱えていたモンスター案件は、ベトナムへのオフショア開発で無事に完了できました。
今回の依頼が僕自身にとって「初めてのオフショア開発」でした。
実際に経験してみて「良かった・悪かった」と感じた5つのことを紹介します。
低コストで委託できた
ベトナムの開発単価は、日本の半分程度です。
そのため、数十名のリソースを割いても低コストで委託できました。
日本のエンジニアより優秀で低コスト。
正直、こちらの立場がないよね。
時差のズレが少ない
ベトナムと日本の時差は「約2時間」です。
業務時間に大きな差がないため、コミュニケーションへの負担を軽減できました。
進捗状況が把握しづらい
単価が低かったので20名ほど人材を確保してもらった結果、進捗状況や問題課題の管理に手間がかかりました。
- コミュニケーションの頻度が限られていた
- 20名分の質問事項がまとめて届いた
状況確認をリアルタイムに共有できるよう工夫すべきだったことが反省点です。
コロナ禍で普及したリモートワークのデメリットに
似ていることかもしれません。
少し誤った日本語もある
ブリッジSEとのコミュニケーションは、問題なくやり取りできました。
しかし、日本語に慣れていないエンジニアには、少しだけ困る要素もありました。
- 質問事項の意図が伝わらない
- ソースのコメントが適切ではない
- 間違った日本語(誤字脱字)を使っている
ちょっとした誤りなので、なんとなく理解できます。
とはいえ、そのままにしておくわけにもいかず、訂正する(してもらう)ことも多々ありました。
規模が小さな案件は難色を示すことも
ベトナムのエンジニアには、モンスター案件の完了後もお世話になりました。
いくつかの案件を依頼しましたが、小規模な案件は旨味がないのか難色を示しがちでした。
たしかに単価が低いから、
利益の少ない案件は引き受けるメリットが少ないかもね。
優秀なSEを確保するならオフショア開発も効果的
今回のまとめ
- 開発スキルが高い
- 仕事に対する責任感がある
- 日本語のコミュニケーションも問題なし
- 低コストで委託できた
- 時差のズレが少ない
- 進捗状況が把握しづらい
- 少し誤った日本語もある
- 規模が小さな案件は難色を示すことも
優秀なSEを確保するならオフショア開発も効果的!
モンスター案件に頭を抱えていた僕は、ベトナムのオフショア開発に助けられました。
開発スキルも働く姿勢も優秀なエンジニアには、恥ずかしながら感心させられたほどです。
ベトナムをはじめとするオフショア開発には「低コスト」のイメージが先行しているかもしれません。
しかし、そこらの日本のエンジニアより「超優秀」と感じることもあるので、優秀なSEを確保する目的で依頼してみることをおすすめします。
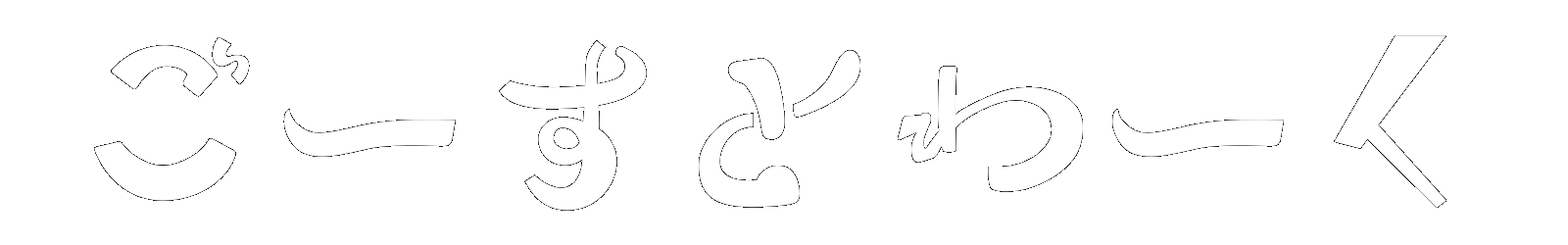
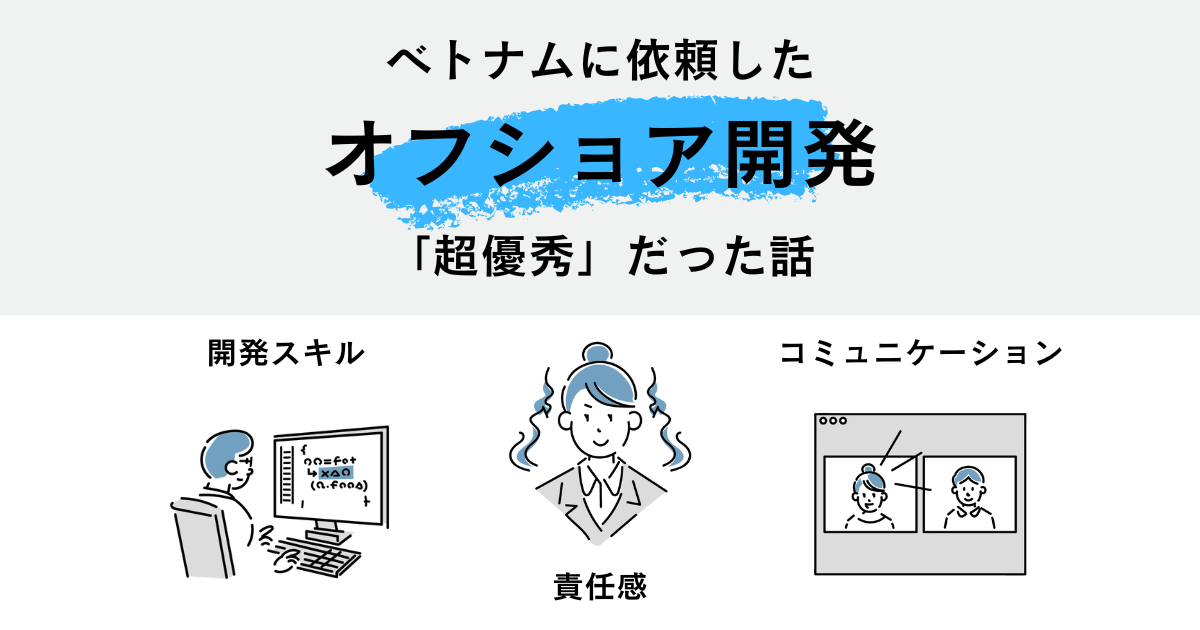
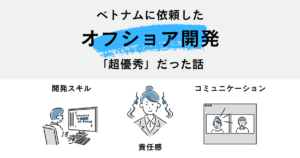
コメント